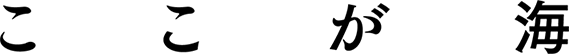Interview インタビュー
※転載抜粋禁止
×
作・演出 加藤拓也
谷生俊美
×
出演 橋本 淳
×
出演 黒木 華
×
俳優 若林佑真
×
ReBit 藥師実芳
映画文筆家 児玉美月 ×
作・演出 加藤拓也

児玉
まず、今回なぜトランスジェンダー男性の物語を描こうと思ったのかというところから教えてください。
加藤
前提としてこの作品の視点は、友理ではなくパートナーの岳人にあります。当事者と非当事者の間にある壁、つまりは自分が当事者ではないということから来る壁に葛藤している人の存在が、この物語の出発点にありました。なので、仮に友理の視点の物語にしていたとしたら、もっと別の展開になっていたと思います。
児玉
脚本はいつから、どういったリサーチに基づいて執筆していきましたか?
加藤
初稿を2023年の4月21日にプロデューサーに送り、その次のステップとして、制作に認定NPO法人の「ReBit」という団体に協力していただきました。カミングアウトのディティールや、受けた側のディティール、また日常的なやり取りに対して友理がどう受け取るのかなど、多岐にわたって対話をしました。定義などの基本的な知識は『トランスジェンダー入門』という本だったり、トランスジェンダー男性が自身の経験について語っているインタビューのサイト(https://lgbter.jp/lgbter/?sexuality=ftm)を読むなど。トランスジェンダーの講師とのワークショップを含め、今のところは第7稿で決定稿となっています。
児玉
そのサイトには120人以上のトランス男性の方々のインタビューが載っているんですね。それだけでも読むのが大変そうですが、いつもリサーチには時間をかけているんでしょうか。
加藤
以前、「わたしはパパゲーノ」というフォームがあって、そこに寄せられたうちの数千件を読んでから『ももさんと7人のパパゲーノ』というテレビドラマの脚本を書いたことがあります。希死念慮を抱えた人たちのドキュメンタリーを撮っているディレクターがいるんですが、子供たちの自殺率が増加する8月末に、そのことに関する物語を放送したいと相談されたことがきっかけです。それを書くにあたって、どのような言葉も簡単に言えないし、まずは彼らを知ることからはじめないといけないということで、数千人分の文章を読みました。リサーチに関しては僕の場合、起きたイベントが知りたいというよりは、その人がどういう感情になったのかということに対して、自分の気持ちがどう動くかどうかが基準になってきます。前提としてもちろん知識は必要ですが、書くエネルギーそのものにはならない。エネルギーが無いと進まないので、時間がかかっている意識は特にありません。他の作品でも同じです。
児玉
基礎的な文献ももちろん重要ですが、評論や論文を書くのではなく、クリエイターとして物語を書くんですもんね。情緒的な部分に重点を置いてリサーチをしているということですよね。加藤さんが以前、作り手として自分自身のアイデンティティから逃げるべきではないと仰っていたのが印象に残っています。どういう角度からリサーチをしていくのかということと、自分がどういう属性や立場にいるのかということは決して無関係ではないように思います。
加藤
仰る通り、『ここが海』が岳人の視点なのは、友理の視点の物語であれば、僕とは立場が違う人が書いた方がいいだろうと思ってしまうからです。自分が同じ立場にいないと、その人の怒りや葛藤や悩みだけを借りてきて、物語で消費することになってしまう。それはダメだと個人的には思いますし、エネルギーにもならず物語も進まないです。僕は岳人とは同じ立場になりうるので、その目線で自分の心が偽りなく動けば書けます。
児玉
岳人の人物像について、加藤さんがこれまで『わたし達はおとな』や『ほつれる』といった映画で描いてきたような男性像とはかなり異なっているというか、非常に理解があって先進的な考え方をしているように見えました。脚本にも、友理のジェンダーアインデンティティを知ったときに、地の文で岳人の反応について「否定的なニュアンスが含まれてはいけない」と書いてありましたね。
加藤
岳人は「理解がある」というよりも、「知識がある」という言葉がしっくりきますね。設定としてライターにしたのは、さまざまな知識に日常的に触れている職業だからです。『ここが海』は、岳人がある程度前提となる知識を持っている状態から、理解、そしてその先へ移りゆくグラデーションの物語です。この作品で書かなければいけないと思っていたのは、グレーな、はっきりとしないグラデーションについてです。物語にするという行為の性質上、はっきりさせる事を求められますが、この作品についてはっきりしているのはグレーだということだけです。この物語のその先については決して簡単ではないですし、そう感じる観客もきっといると思います。それでもその先にあるグレーを否定しないということがこの物語にとって重要だったので、知識がある設定になっているのかもしれないですね。
児玉
理解があるから共存できるのではなく、知識があるから共存できるのだというお話はとても大事ですね。それは個人間の関係だけでなく、社会全体にも敷衍できることだと思います。とくに昨今の風潮として感じますが、「誰」が書いたのかが気にされるというか、つまりライターは属性を問われる職業でもあるので、そういった意味合いもあるのかなと思いました。
加藤
そうですね。やっぱり物語の中にも、そういった要素は入れ込みました。
児玉
今の話とも通じるかもしれませんが、映画界ではその役を「誰」が演じるのかについても、より意識的になっています。加藤さんは以前、演劇では年齢や性別といった俳優の属性が登場人物と必ずしも一致しなくていいと仰っていましたし、映画と演劇ではだいぶ状況も違ってくると思います。映画ではとくにトランスジェンダー役のキャスティングに関して、英語圏ではもっと前からされていたものの、日本では2020年代以降より本格的に議論されはじめたように思います。これまで、トランスジェンダー役の多くをシスジェンダーの俳優が演じてきましたよね。まず前提として「トランス役はトランスの俳優に」という主張において重要なのは、マイノリティ属性にあたる役をマジョリティ属性(として認知されうる)俳優が占有してきたという構造上の不均衡があるという点です。そこにはシスジェンダー中心的な価値観によって差別や偏見を深めてしまうステレオタイプが生み出されてしまうという表象上の懸念に加えて、雇用の機会や賃金における不平等など、さまざまな問題があります。そうした格差是正の措置の第一歩として最低限、数少ないトランスの役にはトランスの俳優を起用するところからはじめていかなければならない段階なのだと。その辺りについて、どういったお考えでしょうか?
加藤
まず、当事者キャスティングに反対しているわけではありません。むしろ仰られている通り、これまでより積極的に行うべきだと考えます。ただ、解像度の低いまま、右向け右で、全員が右を向いて行うのではなく、解像度を上げて何故それが必要なのか?何故その選択肢を選ぶ、または選ばないのか?そういった一つ一つのことを、当事者と直接話をしたり、第三者である優位性に目を配ったり、自分の頭で考えて自分の言葉にしたりして、インターネットだけで自分を取り囲まないことが大事だと思います。アイデンティティポリティクスがかなり進みましたよね。ただ、属性だけに縛られてしまうとどうしても議論が行き詰まってくる部分もあると思います。過渡期だと思うので、過ぎ去ってみないとわからないことかもしれないですね。
児玉
右向け右というか、もっと議論を細分化しないといけないのではと感じるときはあります。もちろん、あらゆる性的マイノリティの俳優の人権や地位がきちんと守られる環境や、そもそもカミングアウトできる風潮が培われなければならないのは前提として、たとえばレズビアンやゲイといったセクシュアリティに関する属性の当事者キャスティングと、ジェンダーに関する属性の当事者キャスティングは、いっしょくたにされがちですが、別の位相の問題として詳らかに捉えていかなければならない部分もあるように感じています。また、トランスジェンダー男性の表象は未だ少ないので、本来は同じ属性だとしてもさまざまな人がいるはずですが、どうしても観客にとって「これがトランスジェンダー男性なんだ」という印象を与えてしまうこともあるかと思います。その点については、どんなところを心がけていましたか?
加藤
先日、ReBitの代表理事である藥師実芳さんをはじめトランスジェンダーの講師たちを招いて、俳優を含めたワークショップを開催しました。色々な話を聞く中で、トランスジェンダーの中でも、カミングアウトのタイミングや、それこそこの作品に関しても、意見が違っていました。つまり当事者でも意見が割れる中で、どういう部分をピックアップしていくべきか、ということが難しいところです。ある意味で一般化させないことが重要で、一般化させない物語にするということには、やっぱり岳人の視点であるということや、この家族の在り方などが働いているのではないでしょうか。
児玉
トランスジェンダーの人物像をどうするかだけではなく、その人物をどういうレンズを通して描くのかということによっても、普遍性や個別性は変わってきますもんね。今の社会はまだまだトランスに対する差別や偏見が厳しい状況でもあるかと思いますが、クィアの物語を描くときに、どれだけそういった描写を入れ込むのかも一つの論点になりうると思います。たとえば近年では、特定のマイノリティ集団に属している人が日常的に受けるさりげない侮辱や中傷、差別のことを指す「マイクロアグレッション」という言葉の認知も高まってきているように、現代の差別の形態はわかりにくくもあり、フィクションにおいても過剰になりすぎてしまうとリアリティが損なわれることもあると思うのですが。
加藤
ReBitさんとも、安易に悲劇にするのは避けた方がいいという話題は出ましたね。悲劇がすべてダメというわけではないし、当事者でない人が書くことがいけないわけでもないと仰っていましたが。ただ今の状況だと、当事者と非当事者の反発し合う感情を作り手が納得させないといけない立場にあるというか、当事者を置き去りにして、非当事者同士だけで攻撃し合っている場合もあるし、そういった複雑な世の中の立場を踏まえれば、悲劇的に描くという選択肢は、今はないと思いました。
児玉
悲劇それ自体が批判されるべきというよりは、安易に悲劇に落とし込んでしまうその構造にこそ批判の目が向けられなければいけないのかもしれないですよね。そうなってしまうのは、作り手側が当事者の声に耳を傾けず、自身のイマジネーションを過信してしまうからかもしれません。物語で描く属性の当事者を置き去りにしないためにどうすればいいのかということを、まず考えていかなければいけないんじゃないかと。その点『ここが海』は加藤さんも「ReBit」さんにヒアリングを行いつつ脚本の執筆を進めていますし、役者の黒木華さんや橋本淳さんもご自身で勉強していたり、ワークショップにも意欲的に参加なさっていたり、事前に対談という形でトランスジェンダー当事者の方のお話を真摯に聞いて演じようともしています。みなさん、できるだけ誠実にこの企画に取り組んでいこうとする意思が感じられます。
加藤
選択そのものでいうと、たくさんの人に受け入れられれば、もしかすると瞬間的には正解かもしれないし、これから先どこかでそれが引っくり返ることも十分あり得ると思います。現時点ではやっぱり、悲劇的に描くようなことを僕がやると、どうしても僕以外の怒りの部分を借りているだけになってしまう。同時に悲劇的な部分を描かなければ、現実で起きている悲劇的な出来事を無視しているとも捉えられる。この作品に必要な結末は、先ほども言いましたが、僕に起こりうること、それと細かなグラデーションの移ろいです。ワークショップでも話題にあがったのですが、その移ろいの視点は性自認、性的指向にもあり、その様子が結末に必要だったと言えます。
これ以降は、物語の具体的な
描写に触れます。
児玉
私は脚本を5稿から読ませていただいて、改稿した脚本も読んだんですが、結末部分が変わっていて、よりポジティブに受け取れる物語になっているように感じました。最初は、悲劇とまではいかなくとも、もっとこれまで観ていた加藤さんの映画にあったような、愛の不可能性や誰かと共にあることの難しさといった主題が押し出されているような印象を受けたんですよ。
加藤
5稿もあくまでもポジティブな要素は残しつつも、どうやって一緒にいられるのかという終わり方にしていました。6稿は設定として真琴の年齢を変更し、そのラストに友理と岳人はまだ一緒にいるかもしれないというニュアンスをもう少し強めました。
児玉
5稿の段階だと、友理と岳人の二者間によるパートナーシップの問題を強く感じたんですが、6稿では家族という在り方を問い直していく物語になっているように見えました。
加藤
意図はその点にあります。岳人の、徐々に自分自身のセクシュアリティが変化していく可能性を示唆することです。友理のことを女性として好きだったところから、揺るがされていく。作品の最後に、「岳人はゲイじゃない」という台詞があります。岳人は男性を好きなわけではないことが物語の最後に明示されて、それでも二人は一緒にいれるのかということになっていく。そこでこれまで定義されていた家族だったり、一緒に過ごす人としての定義だったりが、彼らの中で変わっていくということがこの作品の最後にあります。
児玉
グザヴィエ・ドランが監督した『わたしはロランス』を思い出しました。主人公のロランスが35歳の誕生日を迎えたのをきっかけに、パートナーの女性に自分は女性だからこれからは女性として生きていきたいとカミングアウトするんですね。そこでパートナーは、トランス女性として受け入れるのではなく、「なぜゲイだと隠してたの」ととっさに誤解してしまうんですね。トランス女性であり女性に性的指向が向くレズビアンだと徐々に理解していくわけですが、その過程で自分はレズビアンではないから変化していくパートナーを愛し抜けるのかと葛藤するという。トランスジェンダーの女性であれば男性が好きなはずだ、トランスジェンダーの男性であれば女性が好きなはずだという異性愛主義に基づいた思い込みはまだあるので、トランスジェンダーであり同性愛者であるという設定にも意味があるように思います。さらに、友理は現状では胸オペだけを望んでいるトランス男性という人物造形にもなっていますが、その辺りはどうやって決めたのでしょうか。
加藤
胸オペのみの設定は2稿から設定されました。生殖器の手術には、相当なリスクを伴います。年代の設定も改稿で細かに変わっていき、2023年の段階では、戸籍上の性別を変えるために手術が必要なのは違憲だとする判決がまだ出ていませんでしたが、2023年から2024年にかけて判決が出て、戸籍上の性別変更の要件を定めた性同一性障害特例法の解釈を巡って変動があったので、2024年であれば、手術の有無にかかわらずホルモン投与のみで戸籍上の性別が変えられる可能性がより高くなり、当事者や有識者の観客が観たときに、ここはどういう背景や事情が絡んでいるのだろうかという疑問を感じにくい設定にしています。

児玉
実社会の司法制度上の動きに対しても目配りがあるということですが、そういった具体的な情報は、物語では言語化されていませんよね。友理と岳人が離婚するかしないかを話し合う場面でも、そもそも日本では同性同士に対して婚姻も認められていませんし、男性に移行するなら同性同士のカップルになってしまうので、特例法でも非婚要件が設けられているために離婚しなければならない。そのくだりはオミットされています。何も知らない観客に対してどれだけ丁寧に情報を与えていくか、そういった啓蒙的な側面との兼ね合いについては悩みましたか?
加藤
法律や制度の話を入れるという選択肢もあるかもしれないですが、お客さんにゼロから教える教科書ビデオではないので、難しいところですね。
児玉
あくまでフィクションなので、現実の司法制度は一旦置いといておくこともできますし、そうでなくともそういうところから距離を置く登場人物たちとして描く選択肢もあったかと思います。そうせずに、脚本を実際の社会と連動させていった理由をもう少し教えてください。彼らはあくまで司法制度に則って生きていこうとしますよね。
加藤
友理にとって、戸籍上で男性の性別を取得するのが大事だと考えている時期があり、紙上の手続きが意外と自分たちの行動をコントロールしていたんだと実感するシーンが最後に出てきます。自分にとって大事なことだったから法律に則って行動を取ろうとしたし、それを岳人も理解しようとした。そのことがどれだけ大事なのかは、本人にしかはかれないことですよね。戸籍を変えなくてもそれでいいという人もいれば、認められたことを形としてほしい人もいて、色々な人がいると思います。
児玉
友理の環境は、自分の望む選択をしていくにあたって、ある意味恵まれているようにも見えます。それは人間関係だけでなく、経済的な問題にしてもそうです。この社会にはトランスジェンダーに対する雇用上の差別などが歴然とあり、シスジェンダーよりも貧困率がずっと高いですよね。そしてもちろん、トランス女性とトランス男性の間にもまた格差があるわけですが。友理はノマドのライターで生活に不自由はしていなさそうで、トランスにとってさらに負担として背負わなければならない医療的手段に伴う費用を賄う経済力もある。加藤さんの『ほつれる』は、最初の方にグランピング施設が出てくるんですよね。グランピングって相場が高いので、キャンプではなくグランピングを選ぶ人たちの物語なのか、ということが観たとき新鮮にも感じて、強く記憶に残っていたんです。それを加藤さんが「日本映画には中々描かれない階層の人たちがいる」と指摘してくださって、ハッとしました。
加藤
それは、白か黒かを付けたがるというか、答えが出ていないことに対するアレルギーが強いからだと思っていて。企画を通す側が、よく見る光景じゃないと判断ができないということが大きいですよね。だからクリエイター側も、よく見る光景を思いつくようになる。よく見る光景を「王道」だと思っているクリエイターとプロデューサーが、すごく多いということなのかもしれません。「王道」というのは、「ドキドキする」とか「ハラハラする」とかそういう抽象的な感情のことだと思っているので、すでに知っているものを「王道」だと考えている文化には違和感を感じます。
児玉
もう一つ、脚本の変更点について気になったのは、友理の生理用ナプキンを入れたポーチを持っている描写が付け足されていますよね。あえて物語に「女性」としての記号をひとつ増やしたというのは、どういった意図があったのでしょうか?
加藤
それは、友理のジェンダーが移行していく段階を見せるためです。脚本が演劇になっていったときに、髪型や服装などの外見であったり、所作であったり、そういったグラデーションをもう少し丁寧にしたいと思いました。
児玉
最近の映画でも、トランスジェンダーの登場人物を描くにあたって、手術を受けた瞬間「男性」から「女性」に「生まれ変わった」かのような展開がありました。「性転換手術」ではなく「性別適合手術」と呼称するようになったのも、一つには「性転換」の語感がトランジションをコインの表を裏とひっくり返すような実情にそぐわない二面的なイメージのものとして捉えられてしまうからだったはずですが、映画ではそうしたゆるやかなプロセスや機微が蔑ろにされている場合も少なくありません。それはまさに、「性転換」という言葉が使われるときに暗に含み込んでいるように感じられる、性別移行に対する非現実性のようなニュアンスと親和的な表現の在り方だとも思います。
加藤
それは、映画というフォーマットと興行の欠陥なのかもしれないですね。構造上、こう進めた方が観客を飽きさせないとか、コマーシャリズムの入った視点のフォーマットが教科書として存在しているから、そういうことが起きてしまうのかもしれない。演劇は物語をこう語らなければならないというようなフォーマットからは、ある程度自由というか、そこに従いたくないと思っている人が多い分野ではあるように思います。たとえば配信系の作品なんかだと、何分ごとに何が起きて……という風に定められた、あらゆる映画やドラマに当てはめられるフォーマットが存在します。ハリウッドにしても合理主義というか、興行としていかに成功するかに焦点が当てられていますよね。ハリウッドに脚本を売る場合は、そこに則っているかどうかをつねに見られてしまう。
児玉
日本の演劇界は違うんでしょうか?
加藤
演劇は、良くも悪くも、そういったメソッドが普及していないですね。日本の演劇界においては、型があるというよりはむしろ、前の世代がやっていたことと違うことをしようとするカウンターカルチャー的な傾向があります。2010年代以降、海外の演劇によりアクセスしやすくなりましたが、ロンドンの演劇とかだとかなり体系化されているので、演劇もそうした方が見やすいということに人が気づいていますが、逆にロンドンの人達と話すと、飽きている人も沢山居る。
児玉
今のお話を踏まえると、『ここが海』が映画だとしたら、まったく違うものになっていたかもしれないですね。
加藤
映画だったら書けないです。『ここが海』は、演劇向きですね。
児玉
では逆に、『わたし達はおとな』が演劇になったりもしない?
加藤
ならないですね。映画と演劇の一番の違いは、目の前に生の時間があるかどうか、観客と同じ時間を共有できているかどうかだと思います。映画は、スクリーンと観客の時間がそれぞれ分断されている。映画一作目で一番苦労したのが、カメラがそこにあるということでした。カメラで撮っているということを観客に意識させないのが映画の基本としてありますが、カメラの存在を僕は無視できなかったんですよね。観客がカメラに気付いていないフリをしていて変だと思った。だから、あえて狭い部屋の撮影でも85~135mmの望遠レンズを使って、明らかにそこにカメラがあって覗き見しているような感じにしました。そうすると演劇的な空気感も出ますし、そういうレンズ選びをしていたんですけど、二作目の「ほつれる」になるとまた感覚が変わって、今はカメラを普通に認識できるようになりました。
児玉
加藤さんにとって映画というのは、カメラとの関係を捉えていくことなんですね。それは演劇畑の人ならではという感じもします。
加藤
決して面白いとか面白くないの軸だけでははかれない作品には、自分で物差しを繕わないといけない。今の時代はそういう「わからなさ」みたいなものが中々受け入れられない時代でもありますが、その中で自分が何を作っていけるのかを考えているところです。この作品を上演する意味の中で、座組にいるすべての立場の人が、どんな物差しを繕うべきかといったことも重要な要素ですし、そんな話を座組と続けています。
(文・児玉美月)
映画プロデューサー 谷生俊美 ×
出演 橋本 淳

橋本
谷生さんのご著書の『パパだけど、ママになりました』が本当に面白くて、3回も読み直しました。今日はこの本の中にも登場するパートナーの「かーちゃん」さんのことなども含めて、色々お話できたらと思います。今回『ここが海』で僕が演じる岳人役がカミングアウトをされる側なので、立場的には「かーちゃん」と近いんですよね。ここ一年くらい性的マイノリティについて勉強している中でまだまだ疑問も多いので、今日はそのあたりもぜひ聞いていきたいです。
谷生
この対談に際して事前に橋本さんのほうから質問案をいただいていましたが、とても真摯に考えていらっしゃるのが伝わってきました。私もトランスジェンダー女性であり、子どものいる家庭を持っているという状況が『ここが海』の彼らと近くて、深く沁み入るものを感じました。ただ私の場合、パートナーとは付き合った当初から今の姿でしたので、長年連れ添った相手から突然打ち明けられて関係性が変容していくということは経験しておらず、そこが大きな違いです。
橋本
そうすると、カミングアウトのようなものはとくになかったということでしょうか?
谷生
私は三十代で徐々に性別移行していきましたが、MtFは外見で気付かれるので必然的にカミングアウトしているようなものなんですよね。パートナーも私がフェミニンな姿に変わったことに対してある種の違和感を持ったのかもしれないですが、当時はつとめて冷静に見えました。『パパだけど、ママになりました』を執筆中パートナーにも読んでもらっていたのですが、彼女とのことを中心に書いた章に入っていきなり赤字をたくさん入れられてしまって(笑)。実は、私が付き合いたい気持ちを伝えたとき、かなり動揺していたらしいんですね。「自分はレズビアンではないしストレートだと自認しているけど、谷生さんは女になっているし、どういうふうに理解すればいいのだろう」と。パートナーはアメリカで社会福祉を学んでいたんですが、大学院での学位取得の際にジェンダーやセクシュアリティについて学べるような授業があったらしく、ある程度知見がありました。日本よりもアメリカの方がそういう情報にアクセスしやすいので、たくさん文献や資料などを読んだらしいんです。そうした中で得た知見なども理解の助けになったのか、性的指向などは関係なく、「私は谷生さんという人間が好きなのだからそれでいい」と自分を納得させられるようになったということでした。
橋本
『ここが海』では、岳人がパートナーからトランスジェンダーであることをカミングアウトされます。岳人の受け取り方は、当事者からするとどういう反応に見えたのでしょうか?僕自身、もし誰かにカミングアウトされたら、どういう反応が正解なのかいまいちわからなくて。
谷生
私は立場が少し違うので想像になってしまいますが、岳人は本当に優しい人だと思いました。こんなに寄り添ってもらえたら素敵だなと。逆に、友理の決意が固すぎるところが岳人を苦しめている部分もあるかもしれない。友理がそれだけの決意をしたからこそ緊張感のある関係になったのだと思いますが、受け止め方という点では岳人は素晴らしいですよ。
橋本
色んな本を読んでいると、まずは相手の話をすべて聞くことが大前提だと書いてあります。これまで改まってカミングアウトをされた経験はないんですが、話の自然な流れでパートナーについて話されたり、暗黙の了解の状況はあります。僕はあからさまに拒絶反応をするわけでもないですし受け入れられる方だと思っていますが、今後そういう状況に遭遇したとしたら、どうすれば当事者を傷つけないのかを知りたくてお伺いしました。
谷生
橋本さんは大丈夫だと思いますよ。私の例で言うと、日本テレビの編成局編成部で「金曜ロードショー」と「映画天国」のプロデューサーを務めていた時に、入社前から見てくれていた上司にカミングアウトしたんですね。いつも人と接する姿勢が柔らかい方で尊敬していたんですが、何かを求めていたわけではなく、ただ話を聞いてほしかったんです。まず、そんな風に話を聞いてほしいと思われる人になることが大事だと思いますね。その上司はカミングアウトを受けて、「こんなに大事なことを私に話そうと思ってくれてありがとう」と言ってくれました。そういう対応が望ましいと書いているLGBTの本なんかもありますが、上司は読んでない気がします。学んだわけではなく、自然にそういう反応ができる人なんじゃないかなと。「谷生さんは、今の“フェミニンな男性”というスタイルが完成系かと思っていたけど、『女子』なんじゃない!それなら加速したほうがいいわよ!」と励ましてくれて嬉しかったですし、どう会社に話していけばいいのか、社内理解に向けてのレールまで敷いてくれたんです。日本では、それなりに勇気を持ってカミングアウトする人が多いので、そういう対応をしてあげると相手は安心すると思います。
橋本
たしかに、そんな風に普通に受け取ることが当然であるべきですからね。現状の日本だと、カミングアウトは大きなことになってしまいますが、普通の会話として話せれば一番自然なんじゃないかなと思います。もしかしたら僕自身、カミングアウトを過剰に問題視してしまっていたのかもしれない。気にすればするほど失礼になるかもしれないし……。
谷生
そんな構えることなく受け止めれば、橋本さんは大丈夫だと思いますよ。
橋本
人生相談みたいになってしまいました(笑)。

谷生
日本だと有名になればなるほど大変になりますし、有名人でもカミングアウトしている人がどのくらいいるかという話ですよね。もちろんカミングアウトすることが必ずしもベストとは限りませんが、もう少し気軽にカミングアウトできる環境があるといいなと思います。
橋本
今のお話とも繋がってくるところかもしれませんが、当事者ではない役者がその役を演じることについて、どう思っていますか?
谷生
これまでハリウッドでは、もともとは黒人の役を白人の俳優が演じる「ホワイトウォッシュ」などが問題視されてきました。たとえば、ゲイ役を当事者ではない俳優が演じることはもうハリウッドでは難しいのではと思うくらい、ここ5年ほどで変わってきています。同様に、日本人役を日系以外の俳優が演じることも批判が出てきています。当事者が演じるのが一番望ましい形という考え方も、もちろんわかります。トランスジェンダー女性であるリリー・エルベの半生を描いた映画『リリーのすべて』で主演を務めたエディ・レッドメインも、最近の時流に合わせて、トランス女性を演じたことは「間違いだった」と発言したりもしています。結論から言えば私は当事者以外が演じてもいいと思っていますが、それはケースバイケースです。ハリウッドの超大作ともなれば、資金力もあって全世界からキャスティングできるので、俳優の選択肢も多い。ゲイとしてカミングアウトしている役者であってもたくさん候補がいます。対して日本では、そもそもカミングアウトしている役者が少ないですよね。その中で当事者を選ばなければならないとなると、違う話になってくると思うんです。いかに真摯にその役に向き合い、理解をし、なりきったお芝居ができるかどうかが大事。当事者ではない俳優が演じることに反対するのは理解はできるのですが、それだけで全てを否定してはいけないのでは、と思います。
橋本
僕も当事者に近い役者が演じるのが望ましいとは思っていますが、そこに限定的になると違うかなと感じていたので、今のお話を聞けてありがたいです。より真摯に向き合って、役に合った人がやればいいのかなと。どのくらい矜持を持って取り組めるかどうかが大事ですよね。
谷生
日本の演劇やコンテンツにおける議論はコンテクストが異なるので、同列には語れないかもしれませんが、当事者の役は当事者が演じるべきではないのかという議論が生じたのは、社会的な背景があります。アメリカにおいて、黒人差別はアメリカ国民の原罪として刻まれているので、人種における当事者キャスティングには重みがありますよね。昔は白人が顔を黒く塗って「おかしくで間抜けな」黒人を演じるミンストレルと呼ばれたショーがありましたが、今では非常に人種差別的であった、というのが共通認識です。また十数年前とかであれば、ハリウッド映画でいわゆる白人がアジア人役を演じることは結構ありました。ただその時に目を細くメイクしたりすることもあり、そういったステレオタイプを再生産してしまうのは良くないですし、そこにはアジア系をキャスティングすべきですよね。
橋本
演劇は、より観客のイマジネーションを利用するものです。僕も6歳の子の役を演じたり、海外戯曲を演る時などは異なる人種を演じたり、姿を変えなくても観客のイメージだけで、その瞬間まったく別の人間になる。演劇では表現の自由として、そのあたりは自由であってほしいです。また、それをしたいと望む誰もがカミングアウトができる、しやすい社会にするためには、どう環境作りしていけばいいと思いますか?
谷生
私が小さい頃は、なかなかロールモデルも見つけられませんでした。今はあらゆる形で情報にアクセスできる世の中ですし、アンテナを立てて生活していれば、周りに性的マイノリティが全くいないような環境はないと思います。こうした状況がより進んでいくと、自然にカミングアウトしやすい社会になっていくんじゃないでしょうか。ただ司法制度面で言うと、差別を禁止する法律は必要だと思っています。そういう議論をすると、「どうしてLGBTだけ優遇するんだ」といった反発がすぐに飛んできてしまうんですが、当たり前の対応をしましょうというだけの話なんですよね。これは女性問題とも通じるところがあって、たとえば百年前なんかだと日本で女性の権利がどれだけ保障されていたか。財産も相続できず、政治活動にも参加できない。それがおかしいという主張に対しては、現代ではもはや異論がないと思います。それでも当時は、まったく理解されなかった。それが先人たちの努力によって、普通選挙が実現し、被選挙権が実現した。それでもなかなか出産や育児などで、女性のキャリアには枷がかけられたまま社会進出は進まず、1960年代以降女性解放運動が活発化していきました。もし今、政治家が「女なんて結婚して子供を産んでいればいい」なんて発言をすれば、直ちに罷免の危機に陥るじゃないですか。それは女性の権利についての共通認識がきちんとあるからです。同じようなことが、LGBTや障がい者といった社会的マイノリティにも当たり前になっていけば、きっと理解は進んでいく。教育やルールによって、自分たちが向かうべき大きな方向性を示すことが大事ではないでしょうか。そういう対話を丁寧にしていくと、何かが脅かされていると感じている人たちの心を、ほぐしていくこともできるのかもしれない。現在のトランプ政権にも象徴されるように、「DE&I(多様性、公正性、包括性)」の考え方について、否定的な感情をもつ人たちの勢力が増しているように見えるので、それが日本にも波及するとまた後退するかもしれないと不安です。こうした見方は、私がマイノリティになったからこそ見えてきた世界なのかもしれません。
橋本
僕は今38歳ですが、学校教育で性的マイノリティについて教えられた記憶はありません。『ここが海』で真琴役を演じる中田さんが今20代前半なんですが、中高の教科書には少し載っていたみたいです。ちょっとずつ変わってきてはいますよね。物心つくくらいの年齢の教育が変わればかなり違うと思うので、まずはそこから見直すべきだと思います。もちろんまだまだ時間はかかってしまうのかもしれないですが。子どもの頃にそういう授業をきちんと受けられていたら、今全然違っていたと思うんですよ。学校教育が不十分なのが、日本が世界から遅れをとっている理由の一つなのかもしれません。なので今回自分で学ばなくてはと思い、『ここが海』にも関わってくださっている「ReBit」さんが監修に入っている本を三冊ほどと、『トランスジェンダー入門』などを読みました。遅ればせながらこの年になってから勉強すると、遅かったなと思ってしまう瞬間もありますね。
これ以降は、物語の具体的な
描写に触れます。
谷生
『ここが海』を読んだ時、終盤で友理が離婚届にサインしようとするけどできないところにグッときました。重みですよね。友理がカミングアウトし、岳人と離婚するという頑なな決意に至り、それを伝える。でも一方で、岳人には今の家族の形をどうにか維持していけないのかという葛藤があって。感じることがたくさんありました。時間だったり、愛だったり、色んなものの重みの中で友理が揺れ動く様がリアルで、「大丈夫だよ」とつい私が言ってあげたくなってしまいました(笑)。
橋本
言葉で決意していても、いざ行動に移すとなると辛くなってしまうんですよね。これから稽古をしていくとまた変わっていくと思いますが、僕自身もやってみないとどういう気持ちで着地するのかがわからなくて、そういう意味では楽しみでもあり、怖さでもありますね。文字ではなく舞台を実際に観てもらうと、また感じ方が変わるかもしれません。『ここが海』のホンは読むたびに変わるのでそれが不思議で、だからこそ丁寧に演じていきたいです。映画と違って演劇は言葉だけで進むので、リズムや音などで肉付けしていく必要がありますが、加藤拓也さんの戯曲ですので、書いていることそのままの感情で言わせてくれないというか、言っていることと思っていることが真逆だったり、セリフ一行一行作っていくのが本当に大変なんですよね。基本的に登場人物たちが話しているのは、嘘や建前なので。
谷生
ああ、やっぱりそうですよね。
橋本
だから本当は、準備するのに半年くらいはかかります。この物語を加藤さん自身の立場から書きたいというのは最初からあったみたいで、そこが誠実だなと思って今一緒にやっています。でもこうして谷生さんとお話しさせていただいているのもそうなのですが、知識をどんどん増やしていかないと、この役を演じることはできないと思っています。先ほど谷生さんに言及していただいた友理が男性として生きていくにあたって、どうしても岳人とは離婚しないといけないという場面についてですが、婚姻制度を利用している場合や未成年の子供がいる場合、一定の条件を満たさないと法律上で性別を変更できないという現行の制度には、疑問を感じています。
谷生
そこには結婚や子どもなど、さまざまな要点があります。私の場合、パートナーとの関係のあり方を模索していく中で、現行の制度だと私が戸籍上の性別変更まですれば、婚姻関係は結べなくなってしまう。パートナーシップはお互いに対するコミットメントだと捉えているので、必ずしも社会的に承認される必要はありません。とはいえ、お互いを守るということにおいて最大化するためには、結婚という手段を取るべきだと思いました。『パパだけど、ママになりました』を出版して、それは男性性を受け入れることに繋がるのでそういう矛盾とはどう折り合いをつけたのかと取材の中でよく聞かれましたが、私は自分自身の幸せを追求するというのが人生のテーマなので、今の日本で生きるにはそれが幸せなんじゃないかと判断し、結婚という選択を取りました。2004年に施行された「特例法」と一般的に呼ばれる「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」には、現に婚姻をしていないこと、未成年の子どもがいないことに加えて、戸籍の性別変更を望む者に対して、外科手術を一律に強いる条件があります。ただ現在では、日本のように過去には性別適合手術を要件としていた国も次々と撤廃していっていますし、日本でももっと当事者たちが性別変更を選択しやすくなるように法改正が進めばいいなと思っています。その一方で今、世界的にトランスジェンダーへのバックラッシュが起きていて、それはどうしてなのかをずっと考えているんですね。かつて「Gender Identity Disorder」に「性同一性障害」という診断名が与えられていたところから、トランスジェンダーの脱病理化が進み、世界保健機関(WHO)が「性別不合」へ、アメリカ精神医学会が「性別違和」へとそれぞれ変更しました。トランスジェンダーがそうして「病理」から「アイデンティティ」として理解あるいはカテゴライズされるようになっていった社会的な変化を経て、差別主義者が誇張や恣意的な攻撃が含まれる極端な言説を流布するようになった。その現状には、私も恐怖を覚えますけどね。
橋本
僕はヘテロでシスジェンダーだと自認しているんですが、性別の選択欄で「男性」に丸をつける局面で、決め付けられているような感じがしてしまうんです。果たしてその欄には意味があるのか、とも。最近は「男性」か「女性」かだけではなく、その他の選択肢も選べるようになってきてはいますが、そういったカテゴライズしなければならない"縛り"みたいなものに対しての疑問が生まれるようになりました。きちんと決めなければいけないことなのか、そしてそれを明記することの必要性があるのかどうかがわからなくて。どうしても俳優という立場上、声が大きくなってしまうというところもありますし、さらには自身がマジョリティ側に立っていると、意見をしづらいように感じます。こうして谷生さんとお話ししていても、自分の意見を言うことに怖さがあります。
谷生
今のトランスジェンダーを巡るそうしたバックラッシュの中で、何か一言でも口にすることを重く感じさせてしまうような緊張感があるということですよね?
橋本
はい、今日も緊張しています。『ここが海』の岳人役もライターという職業ということもあって、「かーちゃん」さんと同じで、ある程度ジェンダーやセクシュアリティについても知見がある。その上で岳人は人として友理が好きだと自覚していて、前例のない家族を築こうとします。友理と一緒にいる中で、セクシュアリティがゲイになる可能性もありますし、そのままただ人として愛するのかもしれないし、真心なのか情愛なのか、揺れ動いているまま終わっていく話だと思っています。僕自身も岳人と重なる部分がたくさんあって、流動的な感情を形容したくないという思いがあるので、歯痒さを感じているんです。
谷生
自分が何者なのかなんて、結局わからないですよ。でも私は『ここが海』の脚本を読んで、自分はパートナーにすごく負担をかけていると実感しました。友理は岳人に「別れよう」と言うじゃないですか。原因を招いたのは自分なんだと。その姿が胸に迫るというか、友理の気持ちに共感してしまって。それでも岳人は変わらず友理に寄り添うので、もしかしたらその先も家族が続いていくかもしれないと思わせるんですよね。
橋本
切ないですよね。それぞれがお互いのことを思っているのにもかかわらず、相手を傷つけてしまっているかもしれない。それはどんな人同士の間にも起こりうることですし、誰もが抱える問題であるように思います。
谷生
人生には色んなフェーズがあるので、一つの関係の在り方も、その時々で変わっていくものですよね。そういう揺らぎみたいなものの中で人間は折り合いをつけていくはずですが、『ここが海』はそれが関係性にどう影響を及ぼしていくのかということが書かれたお話しだと思いました。
橋本
お子さんも成長していく中で、ここ数年で大変な思いというか、理不尽に感じた出来事はありますか?『ここが海』の家族も、いずれ同じような状況に晒されてしまうかもしれません。
谷生
表に出る仕事をしていると色んな意見を受けますが、一つあるとすれば、理不尽というか悲しみと怒りを覚えるのは「子どもがかわいそう」という意見です。「子どもがいじめられる」とか、「子どもは不幸になる」と言われてしまう。こういう意見には、憤りを覚えます。悔しいし、悲しい。トランス女性が新たな家族形態を築いたことに対して、失礼ですよね。そういう人たちには、子どもの幸せを決めるのは、愛に包まれているかどうかだろうと問いたい。「あなたは幸せなのか胸に手を当ててみてください」と言いたいくらいです。私は、自分の力を最大限に使って、子どもを守っていこうと思っています。ストレートの男女のカップルのもとに生まれてくる子どもが必ず幸せだと、果たして言えるんでしょうか。
実は先週パリに行ってきたんですが、男性同士のカップルが普通に自分の子どもを紹介していたりするんですよ。そういう光景は、ここ10年くらい婚姻の平等というものが西洋諸国を中心に実現してきたからこそ現出してきています。まだまだ見慣れてないがゆえに、違和感を与えてしまう。そこには致し方ない部分もあると思いますが、勝手に子どもが不幸だと決めつけるのは余計なお世話でしかない。子どもに対していかに良い環境を提供できるかですし、だからこそ私はハッピーな物語を届けていきたいと思い、『パパだけど、ママになりました』を書いたんです。
橋本
『ここが海』にも、似たようなエピソードが描かれています。真琴が大麻を吸ってしまった場面で、友理は子供が非行に走ったのは絶対に自分のせいだと周りから言われるだろうと言うんですよね。「関係無い人の方が強い」というセリフがあるんですが、本当にその通りで、第三者自身にはそんな気ないかもしれないですけど、言われた当事者からすると悪意のある言葉はとても重いですよね。
谷生
知らないことで人を傷つけてしまうことは誰にでもあるので、知ることはとても大事です。講演などで、どこまで気を遣えばいいのかとよく聞かれます。「LGBTQ」という言葉を一つ取っても、どこまでアルファベットの頭文字を増やしていかなければいけないのかと。その気持ちもわかります。ですが、そこはあまり原理主義になり過ぎずに知ることが大事だと思うんです、と答えます。人間は、わからないことは怖い。だから差別してしまう。それでも、「差別はいけない」という共通の認識やゴールを持つ社会は、正しいと思います。知らないことへの恐怖は無くならないように、差別もおそらく無くなりはしないでしょう。それでも、不断の努力を続けることに人間性の煌めきがある。幼い頃の自分に同性婚についてどう思うか聞いたら、きっと「変やん」って言ったと思いますよ。なぜなら、知らないから。でも今、諸外国にも行くようになってあらゆるカップルを見ていると、大事なのはそこに愛があるかどうかだとわかります。知るアクションを起こしていれば、人を傷つける可能性も減ります。だからこうして積極的に知識をつけていこうとしている橋本さんの真摯な人柄とプロ意識、もっと言えば人間性を感じられて嬉しいです。
橋本
ありがとうございます。ただ最近、マジョリティの意見が個人の意見としてではなく、一括りにされて消費されてしまっているように感じてしまっています。ここは、どう打開すべきなんだろうと。「お前はマジョリティなんだから」とある形を押し付けられてしまうというか、そういう生きづらさを感じています。
谷生
おそらくそれは、特定の価値観の強要に抵抗を感じてしまうということですよね。マイノリティの権利運動の中で、マジョリティ側に自分が攻撃されているかのように思わせてしまっている部分はあると思います。たとえば女性専用車両をけしからんと思う男性がいますが、どうしてそういう試みが始まったのかということを考えていかなければいけない。痴漢する男性が多い状況に鑑みれば、経済上も社会安全上も、その方がいいからですよね。なのに女性専用車両を利用する女性に憎悪が向けられるのは最悪で、本来であればそうせざるをえなくした社会のシステムそのものに怒りが向かわないといけない。これまで奪われていたマイノリティの声が顕在化してきて、とっさに反発してしまうのかもしれませんが、もっと俯瞰して社会が大きくどの方向に向かっていくべきかを考えられるよう風潮がより広がるといいなと思います。
橋本
人はつい真っ先に見えたものを責めてしまいがちですが、俯瞰して見て、理由を考える冷静さを持つことが解決策なのかもしれませんね。
谷生
私もこういう生き方を選んだからこそ見えてきた世界がありますし、それを発信していきたいとも思っています。その中で、今日は橋本さんのような素晴らしい役者の方と対談ができてありがたかったです。
橋本
講義を受けているような気分でした(笑)。物事は一歩引いて見るということを、改めて自戒として胸に刻むべきだと思いましたし、おかげさまで原点回帰することができました。今日のお話で得たことも、表現活動をして作品を残していく中で、きちんと響かせていけたらと思います。
(文・児玉美月)
俳優 若林佑真 ×
出演 黒木 華

若林
まずは『ここが海』の感想からお話ししていきたいんですが、今まで見てきたトランスジェンダーの作品では、わかりやすく「差別する人」と「差別される人」が二極化されていて、見えやすい葛藤を描いている印象がありました。『ここが海』は日常そのものを切り取っていて、葛藤に関しても誰もが理解できるというよりは、言葉の一つ一つに垣間見える程度に描かれていたのが非常に興味深かったです。言葉一つでかなり印象が変わってくるような作品だとも思いますし、黒木さんがこれをどういう風に演じるのか、あるいは加藤拓也さんがどういう風に演出をつけるのかが今からとても楽しみです。
黒木
実は、まだ具体的にどう演じていくのかはそこまで考えられていなくて。この役に限らず、ほかの誰かを演じること自体難しいことですし、人それぞれ感じ方も違うので、こういう風にお話を聞きながら作っていこうと思っているところです。加藤さん自身も当事者として描くことはできないからこそ岳人の側から書いているとおっしゃっていて。私も誤解のないように演じたいと思う一方で、どうすればその役に寄り添ったことになれるのかが心配なところもあります。
若林
友理自身にもおそらく見えていない部分があるし、そのあたりをどう作っていくのかが難しいのかもしれないと思いました。
黒木
いつも本読みをしながらどう気持ちが揺らいでいくのかを探っていくんですけど、自分自身が経験していない分、どうなっていくのか未知数ですね。だからこうして若林さんにお話を聞く機会をいただけるのは、とてもありがたいです。当事者ではない役者が演じることに対しては、若林さんはどうお考えですか?嫌ではないでしょうか?
若林
あえて前置きすると、僕自身はこの友理役もそうですし、その役の感情や思いを一番伝えられる人が演じるべきで、それが実際に当事者であるかどうかは問わなくていいと思っています。ただ日本の現状を見ると、やっぱり不均衡ではありますよね。映画にせよ舞台にせよ何かを作ろうとしたとき、もっとも重視されるのが視聴率や興行収入で、そうなると数字を取れる俳優をキャスティングしなければならなくなりますが、そこにトランスジェンダーの俳優は含まれない。トランスジェンダーの中にももちろん俳優をやりたいと思っているトランスジェンダーの方たちはいますが、なかなか機会が与えられず、育っていかない状況があります。だからといって、演技未経験の当事者がいきなり主演として抜擢されて、何を伝えたかったのかわからなくなってしまうのもまた本末転倒です。主演はシスジェンダーの役者が務めたとしても、その友人役や、学園ものだったらクラスに1人くらいはLGBTQがいるはずですし、当事者の役者にもできる役はあると思うので、機会が増えていってほしいというのが本音ですね。僕が2022年に『チェイサーゲーム』というドラマに出演したとき、民放でトランスジェンダーの役をトランスジェンダーであることを公言している俳優が演じたのが初めてだったんです。そのとき当事者の子から、「俳優をやりたくてもロールモデルがいないし、なれないものだと思っていたけど、若林さんを見て目指していいと思えた」と言ってもらえたのがすごく嬉しくて。
黒木
きっとその方には、若林さんがとてもかっこよく映ったのでしょうね。
若林
そのとき初めてやってきて良かったと思えました。これまで、「男が女に成り下がっているのは面白いけど、女が男に成り上がっているのは面白くない」みたいなことも言われてきましたし……。
黒木
なんて酷いことを……。
若林
トランスジェンダーで俳優で、幸せに生きていて、それの何が面白いのかと言われたこともありました。「自分がプロデューサーだったらあなたみたいな人は絶対使わない」とか。無理解なことを言われている人たちは、この業界にたくさんいますね。たとえば自分の性を「男性」でも「女性」でもないと認識しているノンバイナリーの子が、あるタレント事務所に入ろうとして面談をしたときに、向こうから「全然可愛いじゃん、無理しなくても女の子でやっていけるよ」とか言われて、結局入るのをやめてしまったこともありました。
黒木
トランスジェンダーの俳優さんは、海外の方が多いですよね。
若林
そうですね。エリオット・ペイジさんも、トランスジェンダーをカミングアウトして活躍しています。ただ、トランス男性を描く作品は世界的に見てもかなり少ない。
いわゆる”オネエタレント”としてテレビに出ている有名人は、煌びやかなメイクで口調や仕草も派手ですが、僕たちトランス男性は見た目も派手ではなく、話し方も特徴的ではないので、それの何が面白いのかという話なのかなと思っています。
黒木
それは、表層的なところしか見られていないってことですよね。トランスジェンダー女性やドラァグクイーンのタレントさんは数多くいますが、トランスジェンダー男性やレズビアンの方はあまりテレビのバラエティ番組などに出てこない。本人たちが表に出たがっていないからなのかと思っていましたが、そうではなく受け手側の問題というか、需要がないからということなのかもしれないですね。
若林
テレビは面白くないといけないという風潮があるからこそ、笑い者にしやすいゲイやトランス女性の方が使われてきました。ただそれによって、たんに日常を生きている当事者は不可視化されてしまったという現状もありますし、そこは変えていかないといけません。
黒木
若林さんは性的マイノリティについて発信する活動をしながら、役者としても表に出ているわけじゃないですか。たとえばさまざまな役を演じる中で、どんなことを感じたりしていますか?
若林
以前、『52ヘルツのクジラたち』という映画で監修を務めさせていただいたんですが、役者として出演もしたんです。それが男性役で喧嘩もあったり、結構暴力的な感じの役で、難しかったですね。
黒木
どの辺が難しかったですか?
若林
カッとなって暴力を振るうようなことも僕自身はまったくないですし、女性が多い環境だったので馴染みがないというか。中高も女子校で、大学も女友達が多くて、暴力的な場面に出くわすこともなかったので、難しかったですね。ほかにトランスジェンダーの役もありましたが、そっちの方が自分の経験もあてはめられる分、やりやすかったです。
黒木
私も今回トランスジェンダーの男性を演じていくにあたって、友理はホルモン注射を打って4ヶ月くらいで声も変わっていくので、どんな感じなんだろうと。わざとらしく低くするのもきっと違うし、とはいえお芝居として、ちょっとずつ変化をつけていかないといけない。
若林
ホルモン投与して4ヶ月くらいだと、本当に人によるんですよね。
黒木
そうですよね。事前のワークショップのときにも、すべて人によるというお話を聞きました。
若林
僕の場合は4ヶ月経ったくらいだと、朝起きたときに少し低く感じる程度でした。声が出しにくくなって、頻繁に咳払いをしていた記憶があります。
黒木
周りに女性へ性別移行した方はいるんですけど、男性へ移行した方はいないんです。だからよりわからないというところはあるのですが、おそらく当事者の方もこの舞台を観にいらっしゃると思うので、男性へと移行していくにあたって所作の変化をきちんと演じないといけないと思っています。わざとらしくはしたくないのですが、その「わざとらしくない」というのは一体何なんだろうと。だからワークショップでも、当事者である講師の方に疑問に感じたことを聞きました。4ヶ月だと身体はどう変化するのか、精神的にはどんな状態なのか、とか。
若林
「わざとらしくしたくない」と今おっしゃいましたが、僕はあえてわざとらしく振る舞う時期もありました。移行期だとまだ周囲から「女性」として認識されてしまうので、大袈裟に男性っぽく振る舞うことでアピールをするしかなかった。だから、仮に友理がそうなったとしても決しておかしいわけではないと思うんです。ただもう一つポイントだと思っているのは、岳人の前だとどうか、というところです。僕は、過去に男性とお付き合いしたこともありますが、今の姿では絶対に元カレには会えないです。トランスしたことすら知ってほしくない。
黒木
どうしてですか?
若林
恥ずかしいというか、当時は必死に「女性」として相手と付き合おうとしていたこともあって、男性である自分を見られるのが嫌なんですよね。僕は、家族の前でも「僕」という一人称を使ったことがないんですよ。そこも自分の中での葛藤で、相手をがっかりさせたくないし、傷つけたくない。父親に会うときは毎回髭を剃って行ったり、ご飯を食べるときもマスクを顎のところまで下げたりとか。父親は気づいていたとは思うんですが、目の当たりにさせてがっかりさせたくない。「女性」として生きられなくて、申し訳ない気持ちもあるんですよ。だから『ここが海』も、友理は外では男らしく振る舞っているかもしれないけど、岳人の前となると今まで通りを演じようとしている可能性もあって、どこなんだろうと。
これ以降は、物語の具体的な
描写に触れます。
若林
僕は『ここが海』をどうしても友理目線で読んでしまいますが、実体験に近いところもありました。加藤さんがどういう意図で書いたのかはわかりませんが、友理のカミングアウトのセリフが「女じゃないかもしれない」でしたよね。その後も「男になりたいって思っているかもしれない」と続き、断定ではなく「そうかもしれない」というニュアンスで言っていますが、僕もそうだったんです。僕の場合、断定にしてもし相手からネガティヴな反応をされたら自分の心がついていけないかもしれなかったので、本当は心の中でわかっているのに、「かもしれない」とぼかして伝えたことがありました。
黒木
大切な人に自分のことを伝えるのは、やっぱり緊張しますよね。
若林
初めて親友にカミングアウトしたときは、バイトが12時に終わってもう終電もないけど、今しかないと思って原付を走らせて。夜中の1時に呼び出したのに、結局2時半くらいまで言えなかったですね。父親には、胸の切除手術のことは事後報告だったんですよ。今日こそ絶対にカミングアウトするぞと決めていましたが、これで関係性が変わってしまうかもしれないと思うと、なかなか言い出せなかったです。
黒木
手術をされる前に、ご両親は気づいていましたか?
若林
カミングアウト自体はしていました。二十歳の誕生日を迎えて、「父へ」と書いた茶封筒の中に便箋7枚分の手紙を入れて玄関の前に置いておいたんですけど、メールで返信が来るまでの時間は、生きた心地がしませんでした。父親はそのただならぬ雰囲気の封筒を見て、僕がこの世からいなくなってしまうのではないかと思ったらしいんですが、読んでみたら違う内容だったのでそこは安心したと。ただ、「トランスジェンダーではないんじゃない?」と言われたんですよ。当時はこの社会に色んな人がいるんだという共通認識もまだ希薄ですし、トランスジェンダーといえば、『3年B組金八先生』の上戸彩さんが演じた鶴本直のイメージしかない。鶴本直は自分の声が嫌で喉をフォークで刺してしまったり、制服もずっとロングスカートを着ていたりしていましたが、僕はそういう感じではなかったし、ロールモデルもいなかった。だからきっと父はそう思ってしまったんだろうなと。
黒木
皆さんのお話を聞いていて思ったのですが、トランスジェンダーの男性は、移行前はどちらかというと女性的だった方が多いのでしょうか?胸が大きかったとか、スカートを履いていたとかおっしゃる方がいました。私自身は、メンズ服が大好きだし、昔は自分の女性性が嫌だったこともあります。胸が大きくなることにも嫌悪感を覚えてしまう時期がありました。「女性」として見られるのが苦手だったというか。
若林
僕はむしろ逆かもしれないですね。バレないように、あえて「女性」らしくしていました。中学時代、同じクラスの子が好きだったんですけど、気づかれないように髪の毛を伸ばしたり、メイクをしたりしていました。それで男の子と付き合ったこともありました。持ち始めたばかりの携帯に、女子校だったので男友達は何人かしか登録されていなかったんですが、誰だったら付き合えるのかを考えながら片っ端から誘って、その中で自分を好きになってくれた子がいて。彼氏がいるという体にしておけば、好きな子に可愛いとか言ったとしてもいわゆる“変な目”で見られないだろうと思って、頑張って「女の子」として生きようとしていた時期もありました。
黒木
それは大変ですね。男友達として仲良くしていた相手と付き合って、続くものなんですか?
若林
一年くらいは付き合ったんですけど、好きというよりは、憧れだったんです。僕にはないものを持っているような人で、「こういう男性として生きたい」と思える相手でした。たとえると『花より男子』に出てくる道明寺司みたいな人で、男の中の男みたいな感じの中に優しさもあって。思春期なので性的なことにも興味を持ってくると、キスしたりするんですけど、仲の良い男友達にされているような、ちょっと変な感じでした。当時は、違和感を違和感として認識できていなかったんですよね。その後、決定的にダメになったのは、キス以上の行為になったときでした。この人とはできないなと思ってしまって、別れたんです。その後、中学から好きだった女の子と奇跡的に付き合えて初めてセックスしたら、幸せすぎて涙が出たんですよ。ああ、僕は女の子が好きなんだって。そこでもう逃れようのない感覚になったというか、そこからどんどん葛藤が生まれていきました。
黒木
そこからだったんですね。もうこれはどうしようもないんだと。
若林
でも知識がないので、当初は自分をトランスジェンダーではなくレズビアンだと思っていました。「女の子」として女の子が好きなんだと思っていたんですが、よくよく考えたら、僕は好きな子の彼氏になりたかったんだと。周囲に女の子同士だと思われるのも、その子に「女の子」として扱われるのも嫌だったし、髪の毛も長かったのをショートカットにして服装もボーイッシュにしていったんですが、高校三年生のときに学校で受けた性についての授業で同性愛と性同一性障害の違いについて教えてもらい、初めて自分はトランスジェンダーだということを確信しました。
黒木
今のお話で言うと、岳人と友理は子供まで産んでいるわけじゃないですか。それでも岳人は、もともと持っていた知識を前提にして、友理を受け入れようとする。子供も大きくなっていて、ちゃんと自意識がある子に対して自分はトランスジェンダーだと伝えなければいけないのは大きなことだと思います。ただ、岳人と友理は家族としては成立しても、夫婦としては成立していかないかもしれない。ワークショップでも、当事者の方から関係性が崩れていってしまった経験談などもお聞きしたので、色々考えました。
若林
僕の知り合いに、「女性」として結婚したのちにトランスジェンダーであることをカミングアウトして、その後も夫婦関係が続いている方がいます。その人がホルモン注射を続けている中でやっぱり子供を持ちたいという話になったときに、とは言っても「母親」にはなりたくない。そこの葛藤があるんだと言っていて、なるほどと思いました。一度ホルモン治療をしている以上、どうしても確率的には低くはなってしまうので、妊娠できるかどうかはわからない状況みたいですね。
黒木
ホルモン注射を止めれば、また生理も始まるんですよね?
若林
それはそうなんですけど、たとえば声は一度低くなるともう戻らないんですね。髭も生えなくなるかと言われると、そうではない。戻らないものもあります。
黒木
子供がいずれ欲しくなるかどうかとか、そればかりはわからないですものね。
若林
今から性別移行しようとしているタイミングで、そこまでのことを考えることは中々難しいですよね。僕も最初は、絶対戸籍も変えて、女の人と結婚して、ペニスも形成して、と思っていました。でも社会的に男性として認められるようになってからは、今まで嫌だと思っていたことが嫌じゃなくなることもあります。
黒木
社会的に男性として認められていると感じられることに大きく関わってくるのは、戸籍を変えたことでしょうか?
若林
戸籍というよりはまず第一に、初めて会う人から「お兄さん」と言われるか「お姉さん」と言われるか、世間から自分がどう見られているのかが大きいです。いわゆる移行期と呼ばれるくらいの時期は、どちらの性別なのかを聞かれることが多くて。これは僕の偏見かもしれないですが、関西の人たちって、思ったことを何でもすぐ口に出すじゃないですか(笑)。
黒木
関西人は多いかもしれないです(笑)。

若林
だからバイトをしていても、もう3人に1人は聞いてくるんですよ。最初の頃は、「どっちやと思いますか?」とか「ご想像にお任せします」みたいな感じで返していましたが、途中からはもう疲れてきて、流していました。それも面倒なことの一つでしたし、カミングアウトしているのにまだ見た目が女性的だと「彼女」と言われてしまったり、男女で分かれるような場面でも女性側に呼ばれたりとか、男性として見られていないことがつらくて。なのでホルモン注射をして髭も生え始め、男性として認識されるようになってからは、すごく楽になりました。胸の手術の後は、さらにですね。僕は去年、戸籍の性別を変えたんですが、身分証もすべて男性に変わって、病院や区役所に行くこともこんなにスムーズなんだと驚きました。
黒木
『ここが海』で、変わりゆく状況の中で友理は岳人とインタビュー記事を作ろうとするじゃないですか。それは、2人が書く仕事をしているからこそ、冷静に話せているということでもあると思うんですけど。
若林
自分のことを誰かに書いてもらうなら、当然ちゃんと書いてもらえる人がいいですね。取材の機会をいただくこともありますが、いざ回答して記事を見てみると、本当に聞いてた?と思ってしまうような内容のときも結構あります。おそらく前提知識がまったくないからだと思うんですが、そうならないように友理は岳人にお願いしているんでしょうね。
黒木
そうでしょうね。ずっと一緒にいる相手ですし。
若林
友理の場合、グレーだから難しくもあり、だからこそ岳人と2人で書くのかもしれないですよね。
黒木
すごいことですよね。加藤さんの書く描写は、本当に細やかだなと思います。たとえば友理が生理ポーチを持って出てきたりするところも。男性に移行すれば、もう夫婦ではいられなくなってしまうとか、まだまだ難しいことがこの社会にはたくさんあるんですよね。
若林
トランス男性に関しては、一昨年から子宮や卵巣を取らなくても法的な性別変更が可能になりましたが、友理のように現に婚姻関係にある場合や未成年の子がいる場合は法的な性別変更はできないですし、仮に条件を満たして変更したとしても、日本では同性婚はできないので、岳人と法的な婚姻関係を継続するのは難しいなど、まだまだ社会的な課題は残されていますね。友理がもっとも心配しているのは本当にそこだよなと思うんですが、果たして相手が変わっていく自分をどこまで好きでいてくれるのか。関係性が変わってしまうかもしれないことを、すごく気にしているんだろうと。
黒木
ワークショップのときに当事者の方が、最初は旦那さんも認めてくれていたけれど、最終的には別れてしまったというお話をしてくれました。見た目も変わっていくし、それは仕方のないことだとおっしゃっていて、それを責めることもできないですよね。友理もそこを気にしているのが、よく伝わってきます。子供の親である事実は変わらないけど、いわゆる「母親」ではなくなるし、どうなっていくのかと。
若林
変わらないだろうと思っていた関係性が変わってしまうことはありますね。学生時代の友人関係にしても、もうあの頃には戻れないんだと寂しさを覚えるくらいには変わってしまった気がします。性別を超えて、多くの男女では成立しないであろう友情関係を自分たちなら成立させられると思っていたんですが、年を重ねて男性へと移行していくにつれて変わってしまいました。友人にパートナーができて一対一の関係ではなくなったときに、あまりにも距離が近すぎると、向こうの相手からもよく思われないですし。
黒木
それはそうですね。
若林
束縛の激しい彼氏と付き合っている女友達に、2人でご飯に来ていることを彼氏に言ったのか聞いたら、「ついてないんだったらいい」と言われたらしくて、「そいつ呼んでこいよ」とか話していたんですけど(笑)。
黒木
性が変わることで、自分と相手との関係まで変わってしまうのは寂しいですね。
若林
僕は恋愛対象は今の所女性だけなんですが、周りには、元々は女性だけが対象だったけど、男性も対象になったという方もいるんですよ。「なった」という言い方をあえてしているのは、性別移行前は「女性」として認識されて男性からアプローチされていたので恋愛対象だと思えなかったけど、男性として認識されてアプローチされると感じ方が異なり、性別移行後に男性とお付き合いする人もいたりしますし、相手が自分をどういう性で認識しているかによって、関係性のあり方って変わってくるんですよね。
黒木
トランスジェンダーの男性が男性を好きになる場合は、ゲイということになるんですか?
若林
恋愛対象が男性なので、ゲイと自認する方もいれば、バイセクシュアルやパンセクシュアルと自認する方もいますね。そのあたりは、本人がどんなふうに自分を捉えているかによって違ってきます。
黒木
そういうカテゴライズって難しいですよね。
若林
それで言うと、僕の付き合う女性は、男性としか付き合ったことがないんです。じゃあその子が僕と付き合ってバイセクシュアルやパンセクシュアルになるのかと言われると多分違うんだろうなとは思いますし、そういうカテゴライズの難しさはありますね。
黒木
LGBTQ……というように、分けると難しいなと思います。その人をただその人として見ると簡単というか、私としてはその方がシンプルな気もしてしまうのですが、そういうわけでもないのかもしれないですね。
若林
僕の場合は、「トランスジェンダー」という自分をカテゴライズできる言葉があって安心できたという側面もありますが、一方で、相手との関わりの中では、その方ならではの困りごとは考慮しつつも、黒木さんのおっしゃるように「その人をただその人として見る」というのがいいのかもしれませんよね。そして、エンタメにおいては、描かれやすい属性と描かれにくい属性がやっぱりあって、トランス男性は描かれること自体が本当に少ないからこそ、『ここが海』は貴重な作品だとも思います。今まで、こんなにトランス男性を描く物語で日常を切り取ったような作品を見たことがなかったです。絶対に観に行きますね。
黒木
そう聞くと、より頑張らないといけないと思います。観てくださった人たちに、登場人物たちが異なる立場をどう生きているのかを感じてほしいです。それぞれが歩んでいる日常というものを伝えられたらいいなと思います。
(文・児玉美月)
公演後に振り返る、
作品について
そして、演劇界の
現在地と未来について
作・演出 加藤拓也 ×
俳優 若林佑真 ×
ReBit 藥師実芳

10月に全公演が終了した「ここが海」ですが、上演しての反響はいかがでしたか?
加藤拓也(以下、加藤)
岳人の立場の物語として理解できること、できないことの感想や、今回に関しては若林さん経由で嬉しいお言葉を頂くことが多かったです。
若林佑真(以下、若林)
勝手に感想を送りつけていたんですよ(笑)。僕の周りのトランスジェンダー男性の当事者たちも、僕が何か言うまでもなく自ら観にいってくれて。いろんな感想を頂いたんですが、一番多かったのが「自分の過去を思い出しました」という声。性別移行期の葛藤や、家族にカミングアウトした際の小さな違和感などが、自分の体験と重なったそうなんです。それは物語と感情がリンクしないと起こり得ないことだと思うので、それは加藤さんの脚本や構成、そして黒木さんの演技の力だろうなと感じています。
藥師実芳(以下、藥師)
私の周囲では演劇が好きな友人からの反響が大きかったですね。テーマ関係なく加藤さんの作品と聞いて観にいったら、偶然僕の名前があったのを知ったという感じで。もともとLGBTQ+の物語に興味があった訳ではない人たちのところにも届いたというのはすごく意義があった。また本作はトランスジェンダー男性個人の物語でありつつ、その周りの人との関係の中で生まれる受容や葛藤の物語だったので、LGBTQ+当事者でない人にとっても共感性の高い作品だったのではないかと思います。
藥師さんと若林さんは、本作でそれぞれどのような役割を担われたのでしょうか?
藥師
私は台本の制作段階から携わらせていただき、ディティールや法律面等のファクトを助言するかたちで参加しています。また、LGBTQ+に関する研修を演者やスタッフのみなさんにさせていただきました。そこではLGBTQ+の基礎的な知識だけでなく、トランスジェンダーを取り巻く国内外の状況や、関連する法律などについて学んでもらったほか、実際に子どもを生んで育てられているトランスジェンダー男性に来ていただいて、ご自身の経験を語ってもらうことで皆さんに理解を深めてもらいました。
若林
僕はもともと黒木華さんと対談だけ行う予定だったんですが、稽古が始まってからアミューズさんに演技監修のご依頼を頂きまして。所作や性別移行していく過程の感情のアドバイスなど、加藤さんと黒木さんの相談役として現場に入りました。
加藤
そもそも薬師さんには、稽古の進捗を伺いながらタイミングを見て稽古場に来てもらうという、プロデューサーとの話だったのですが、稽古開始早々に俳優もやっている若林さんにもっと長い時間軸で関わってもらえたほうがいいという判断になりました。特に演劇は稽古期間が長いので、その中でいろんな選択肢が出てきます。稽古の前半で思っていたことが中盤で違うとなったり、シーンの稽古では良くても通し稽古になると違ったり、そもそも通し稽古だけでは気付かないこともある。稽古では進捗と共に変更の必要もどんどんと出てくる。たとえば友理という役に関して言えば、状況は感情の変化を詳細に描く必要があります。カミングアウト後に家族三人でいるときや、岳人だけといるとき、真琴だけといるとき、その状況下で生まれる変化についてはもちろん、友理が「意識的に振る舞おうとしている部分」や「無意識的に出てしまう部分」を黒木さんが更に意識的に選択してどう演じていくかということをきちんと選んで行かなければなりません。とてもありがたかったのは、若林さんは俳優や演出家のタイミングを伺いながら長い時間軸の中で助言してくれたこと。どうしてもシーンを立ち上げていく過程では、全部を一度に把握することはできませんから。
だから状況に合わせて考えられる時間がきっちりあった。演技はもちろん、衣装やヘアスタイルなどについても「こういう演技を選んで、こういう意図なら、衣装やヘアスタイルはこういう選び方をする。なぜなら…」というように、じっくり選んでいけたのはとても良かったです。
若林
衣装やヘアスタイルを合わせて演技をするとまた印象が変わるんですよね。だから衣装を決めた後、黒木さんに「ヤンチャ度をあと10%下げられますか」なんてことをお伝えしたり。
加藤
「ヤンチャ度」というのは、たとえば友理が理想の男性像を目指す過程で、ちょっと過剰に「男性らしさ」を見せてしまう度合いです。時期と年齢、それから家族間の関係性によってや、それを岳人にどこまで見せるかといったバランスが難しくて、その微妙な度合いの判断は若林さんが稽古に一緒にいてくれたからこそ細かくできたことです。シーンや物語の運びを若林さんに伝えたうえで、その度合いがどうかということを判断してもらいました。
若林
そこは本当に難しかったですね。一番大変だったのは黒木さんだと思いますが。ただ僕は演出家ではないので、黒木さんの演技を見て何か感じた際には、絶対に加藤さんを通すことは意識していました。黒木さんにアドバイスをするときにも加藤さんに「これは言っていいですか?」と判断を仰いでいましたね。
藥師
LGBTQに関する専門性と演劇の専門性を両方もったうえで指導や監修ができる人は日本ではとても少ないですよね。だからこそ若林さんが今回入ってくれた意味は大きい。以前アメリカのGLAAD(※)に、監修についてヒアリングをしたときに聞いたのは、基本的に脚本や制作過程、広報に至るまでを「正確であるか」「コンプライアンス上問題ないか」「意図やメッセージが最大限適切に伝わっているか」といった観点から監修する役と、現場で演技を見るLGBTQ+当事者の俳優がセットで入るということ。それにより作品の川上から川下まで、連携を取りながら全部を見ることができるんです。一方の日本では監修は基本的に1人で、かつ特に現場に入るということはかなり少ない。そのなかで今回は2人体制で役割分担して見れた、というのはとても良かったですね。
若林
藥師さんが脚本や法的な部分を担当して、僕は現場を担当するという住み分けをきちんとしていたので、こちらとしてもすごく楽でした。やはり他の作品だとこういう形態は予算の関係で断られることが多いんですが、今回はアミューズさんが本当に誠実に向き合ってくださったんです。
※GLAAD(グラード):メディアにおけるLGBTQ+の公平な扱いを目指しモニタリングや監修などを行うアメリカの非営利団体
アミューズは「同性婚」を認めない東京高裁の判決に対しても、企業としてすぐに声を上げていましたよね。
藥師
ずっとLGBTQ+の作品を扱って頂いていることも当然ありがたいですが、そうして会社として明確にスタンスを示してくれるのはとても嬉しいですよね。勉強会の前から橋本淳さんはいろんなLGBTQ+の本を読んでくれていたんです。そして「ここが海」のキャストの3人も、勉強会を経た後もたくさんの当事者の本やインタビューに自らリーチしてくれていた。アミューズさんも出演者の皆さんも、本当に誠実に当事者のことを知ろうとしてくれていたのがとても印象的でしたし、すごいチームだなと側で見ていて感じました。
若林
「ここが海」についてのアナウンスをする際も、特例法などに言及して「法律上の性別を変えることにこれほどハードルがある」ということを丁寧に解説してくれたり、本当にありがたかったです。
「ここが海」が画期的なのは、トランスジェンダー男性の性別移行のプロセスを、その家族の視点から描いたことにあると思います。これは映像作品でもほとんどなかった視点ですよね。
加藤
ワークショップに来ていただいた方の言葉を借りると、その視点は「第二の当事者」という言葉がぴったりくると思っています。パートナーからカミングアウトを受ける、さらにはその後自分自身のセクシュアリティが揺らぐという部分まで含めて、自分がその立場になる可能性があるじゃないですか。そういった当事者性を感じたことに加え、そもそも性的マイノリティは当たり前に存在していて、僕自身がその当たり前にいる人たちについてリアリティある世界観で書きたいという欲求がある。それらの理由で生まれた視点だったと思います。
監修の2人が初めて台本を読んだときの感想はいかがだったんですか?
藥師
読む前にアミューズさんから「”妻”からトランスジェンダー男性だとカミングアウトされた夫の物語なんです」とお伝え頂いて、その時点で難しいテーマだと感じたんです。特殊なものとして描かれているのではとどきどきしながら台本を読み始めたらそうではなかった。むしろ「大事な人を分かりたくとも分からない葛藤と、それをどう超えていくのか」というテーマを扱っているんだなと感じたのが最初の印象でした。
若林
僕は当初監修という立場ではなく、黒木さんとの対談のために6、7稿目の台本を読ませて頂いたんです。今までのトランスの物語は「辛い・苦しい・死にたい」の三拍子が揃った悲しいものばかりだったので、これほど日常を切り取った作品が出てきたことにまず驚きました。そして加藤さんがどう演出して、黒木さんがどう演じるのか楽しみだなと考えていたんですが、監修として依頼を頂いて監修目線で読んだら、友理が性別移行していく過程における機微の変化を表現しなければならず、「めっちゃムズいやんけ!」って。それくらい読む立場によって感じ方が変わる台本でしたね。難しすぎて途中で加藤さんに苛立ちすら覚えていました(笑)。

ノマド生活をしている家族3人のミニマムな物語だからこそ、力関係のない個と個の対話が描けたと個人的には思うんですが、一方で浮世離れした設定にしたことで社会と断絶されているという意見も目にしました。それも非常に納得する意見ではあったのですが、そもそもこの設定自体どこから生まれたのでしょうか?
加藤
先ほども述べたように自分自身が岳人になり得るということが出発点にあったので、そういう意味でも自分に近い生活にしたというのはあります。かつ社会に対する友理の視点からの葛藤をもっと細かく入れたい気持ちもありましたが、それだと僕ではなく当事者が制作した方がより良いのではないかと思い、やはり「第二の当事者」の目線で描きたいという思いからこの設定を決めました。
若林
確かに”珍しい”家族の形態なので、友理がどのように当事者の人たちとコミュニケーションを取ってるんだろうとか気になる部分もありましたし、その設定に疑問を持つ人がいるのも理解はできますよね。
藥師
最初にお話を頂いたとき、確かに一般的に想像する家族の生活ではないなとは思いました。一方でむしろそうしたからこそ家族の対話を描けたとも思っていて。たとえば育った地元で暮らす会社員の物語であれば、「会社/近所/親族等にどう伝えるのか」という3人の外にある社会の状況が話題にあがらざるを得ない。やはり3人の家族の中で考えに焦点を当て、家族の会話を途切れさせないために、この設定にする意味はあったと思っています。
藥師さんの監修が入ったことで、台本はどのように変化していったのでしょうか?
加藤
まず藥師さんと行ったのは執筆期間中の社会の状況との擦り合わせです。たとえば2023年10月に最高裁が法律上の性別変更要件をめぐって、生殖不能要件は違憲だと判決を下しました(※)。それまでは性別を変えるために性別適合手術が必要という前提で台本が書かれていたんですが、判決を踏まえて書き直したり、時勢に合わせてアップデートしていきました。その時代の現実が載っていることは台本上でも大事だと考えていたので、どの時代の状況にあるのかといったことを合わせていきました。
藥師
最高裁判決などが出る中で、この物語の時代設定はいつなのかという議論はありましたよね。それによって会話の内容も変わってくるので。あと真琴の年齢についてもしっかり話し合いました。現在の法律で性別変更は「未成年の子どもがいないこと」が条件となる中で、もし真琴が小中学生であった場合、友理は仮に離婚をしたとしても性別変更ができず、「性別変更のためにすぐに離婚を選ばざるをえない」という展開は現実的ではありません。また、一見すると岳人からは突然のカミングアウトのように見えたとしても、実際には友理本人の中では長い時間をかけて考え、言おうかどうか葛藤を重ねてきたはずです。いつから葛藤していたのか、なぜこの日、このタイミングで伝えたのか。そうした背景や心理も含めて掘り下げました。台本に明示されていない部分まで詰めておかないと、葛藤や切実さが見えなくなり、万が一にも「無責任な親」と受け取られてしまう危うさがあります。なので台詞などで説明はしていなくとも、すべての部分において納得できる理由があり、筋が通るようにしています。
また友理の背景についてもきちんと詰めていきました。「友理は幼少期に性別についてどう思っていたのだろう。結婚したとき、はたまた真琴が生まれたときはどうだったのか。そして今想いが溢れるように言ったのはなぜなのか…」というように。というのも、子どもを産んだトランスジェンダー男性像が描かれることが極めて少ない中で、それが実像とかけ離れると台無しになってしまう。今までにない題材だからこそ、しっかり議論させてもらいました。
※生殖不能要件の違憲判決:性同一性障害者の性別の取扱いの変更に関する法律(性同一性障害特例法)のうち、法律上の性別変更の要件とされていた「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」を違憲とする判決。
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/seibyoudou/column/51025.html
バックラッシュが激しくなる今の社会状況で、そういった法制度を含むトランスジェンダーの物語を描くことにリスクを感じることはなかったのでしょうか?
加藤
リスクというのは物語を描くことではなく、上演に関する批判についてのことを言われているのかと思います。批判が起きるかもしれないからといって、業界や社会が上演そのものをやめてしまうことがいいとは思えませんし、どうすればいいのかなんて関わっていかないとわからないじゃないですか。
若林
でも絶対に間違っていなくても、外側の意見の方が力を持ってしまい、叩かれた挙句に潰されることも実際にあるわけじゃないですか。それも踏まえてリスクだとは考えなかったんですか?
加藤
精神的にはしんどいですけれど。
藥師
初稿から脚本を拝見する中で特に難しいと感じたことが2つあって、1つがキャスティングをどうするかということ。そしてもう1つが、子どもを産み育てるトランスジェンダー男性とその家族というテーマをどう描くかということでした。社会の理解がまだ十分に追いついていない現状では、前提となる理解が共有されないまま誤解が広がったり、「伝統的な家族観」といった観点から批判が強まってしまう可能性があります。その結果、実際にそのように暮らす当事者やその家族にとってマイナスの影響が及んでしまうのではないか。正直なところ、そこは怖いと感じたし、責任を重く感じて取り組んだ部分だった。
だからこそ「友理が岳人や真琴をとても大事に思うなかで、どれだけ深い葛藤を抱え、それでもなお決断せざるを得なかったか」や「自分らしく生きることと法律上も家族として生きることを天秤にかけさせているのは、本人ではなく制度や社会ではないか」といった部分をどう描くかは本当に多くの議論を重ねました。もちろん議論をしたうえで台詞にはしていないものもたくさんあります。そこはやはり難しいポイントではありましたね。
社会や制度的な背景をどこまで台詞で説明するのか/しないのかという塩梅はかなり難しかったのでは?
加藤
難しかったですね。ただ演劇の場合、映画と違って台本が残って、いつか誰かの手によって再び上演される可能性があります。たとえば違う国や時代の作品が繰り返し上演されているのはご存じかと思いますが、その上演に際して当時の背景や状況をきちんと調べて、研究しながら取り組まれます。「前提となる知識がない人のためにどれくらい分かりやすくした方が良いのか」という議論はありましたが、基本的に僕は「説明を全部セリフにしない」というスタンスでした。つまり登場人物にのみ必要な会話分だけでいいということです。そこであまりに背景知識の無い人だけを目的にした説明をし入れてしまうと、時代が進んで観客の背景知識が変わったとき、上演に選ばれるような作品にはならないと思います。例えば岳人のような設定も成立しづらくなったりしますよね。勿論、説明を完全にゼロにしてるわけではありませんし、直接的に言っていなくても、ある程度観ていけば理解できるようになっていることもあります。でも作品が立ち上がった時に、トランスジェンダー男性からは共感されても、背景を知らない人からは共感されないこともある。
藥師
ただ知識がない人が誤解しないかということはすごく気を付けました。たとえば離婚しなければ性別を変えられないという現行法律に関する知識がないと、友理が自分本意に見えてしまうのではないかなどかなり議論を行いましたよね。議論の上、作中で説明できない情報も、公式サイトでの対談記事やパンフレット、SNSでの弁護士からの解説等で情報を受け取れるようなコミュニケーション設計を丁寧につくれたことにはすごく意味があったと思います。
若林
ただ一つフォロー出来ていない部分がありまして。友理が性別移行していく過程で、最初のうちはポケットに手を入れて低い声を出したり、男らしさを強調する姿があったんです。終盤では落ち着いていくんですが、その「男らしさ」がステレオタイプ的に見えたという意見を結構頂きまして。ただ個人的な感覚としては逆で、見た目とアイデンティティの齟齬がある段階では、そのギャップを「分かりやすい男らしさ」で埋めようとすることは実際にある。その過渡期を表現したつもりでも、背景を知らないとステレオタイプ的に感じてしまう。そこもあえて物語内で説明しなかったんですが、結果的にそう見えてしまった人もいたので難しいなと感じました。
加藤
内面の複雑さを変化として見せようとすると、一周回って単純化しているように見えるのはありますよね。ただその複雑さをあえて分かりやすく強調するのはしたくなかった。それこそ作品の構造的なステレオタイプだと思うので。
人物像の監修はどのようなことから進めていったんですか?
若林
監修する上で友理が難しい人物だと感じた理由の一つは、どんな人物にもできるからでした。台本の中では大きな事件もないので人物像を掴みにくいんですよね。なので最初に複数の人物像をイメージして、「加藤さんの中でどれが近いですか?」ということを確認してました。「たとえば友理はトランス男性でゲイなのか?それとも岳人だから結婚できたのか?」というように。
また友理という人物を想像するために、自分の経験だけでは足りなかったということも難しいと感じた大きな理由でした。なので女性として結婚して子どもを産んだトランス男性にお話を聞かせてもらったんです。いろんなことを包み隠さず教えて頂きまして。たとえば子どもを産んだときの感覚や、”母親”としての自覚があること、一方で看護師さんに「お母さん」と呼ばれるのは嫌だということなど。写真も幾つか送ってくれたんですが、性別移行した後の写真の方が断然幸せそうだったんです。そういうお力を借りながら、友理の人物像を探求して加藤さんと黒木さんにパスしていきました。
加藤
他の演劇作品もですが、台本上で記号的にわかりやすく登場人物を作ろうとは思っていません。それぞれあらゆる側面を持っていて欲しいし、どんな側面があるのか、上演が模索される度に発見できるように書けたらいいなといつも思います。ヤンチャとかお調子者とか記号的な人物造形をしないので、それは本当にご苦労をお掛けしたなと改めて思いました。
若林
本当に!毎日寝れなかったんですから(笑)。でもその複雑な人物を加藤さんの意図や僕の意見を聞きながら、自分の中に落とし込んで表現していた黒木さんが何よりすごかった。
藥師
友理を演じた黒木さんはもちろん、岳人を演じた橋本さんもすごく大変だったと思います。岳人が友理のカミングアウトをどのように受け止めるのかというのはかなり議論したポイントだったんですが、橋本さんがそこについて勉強しようと思ってもカミングアウトを受けた夫側の体験談というものはほとんどないので、そこは自分の想像で埋めていかないといけない。それができたのがすごいなと。
加藤
その点、橋本さんとはかなり話をしました。劇中、同じことを言っていますしね。難しかったのは思っていることをどの程度アウトプットするかということ。内面的な動揺や葛藤をどれだけ友理に見せるのか、見せないにしてもどうすればそれが観客に伝わるのかという塩梅についてはずっと考えていましたね。
黒木さんの演技が素晴らしかったことは賛同するのですが、そことは切り分けて伺いたいのは友理役に当事者をキャスティングできなかったこと。作品全体でこれほど誠実に向き合いながらも、そこができなかったのは何故なのかを知りたいのですが、その点に関して加藤さんの考えを聞かせてもらえますか?
加藤
現在、映画と演劇の業界では当事者キャスティングの重要性が少しずつですが認識されつつあり、特に映画業界ではその取り組みが進みはじめている印象があります。一方、演劇業界においても認知が進んできているとはいえ、興行的な側面とのジレンマからむしろ題材自体に手を伸ばしづらくなっている側面もあるのではと感じています。たとえば当事者の俳優をキャスティングしたいと考えたときに、作家性にマッチしつつ興行的に収益を上げることのできる俳優を探すのは現状とても困難です。海外であれば作品自体を観に来る人が多いからそれでも成立すると思いますが、俳優を目的とした集客の方が多い日本ではそうはいかない。規模を極力小さくすれば実現するかもしれませんが、小さい経済圏でやるだけだと継続は困難です。そうなると作品は少なくなる一方で、業界の認識も変わっていきません。そのなかで我々が次のフェーズに進んでいくために今できる方法が、藥師さんと若林さんに入っていただくことなのかなと思って今回取り組んでいきました。
集客できるトランスジェンダー俳優を育ててこなかった歴史的・構造的な問題がありますよね。
加藤
本当にその通りで、そもそも社会的にも業界的にも、シスジェンダー男性優位な社会の中でトランスジェンダー俳優の雇用や育成の機会が奪われてきたという背景がある。僕自身その業界にいた人間の1人として、その状況を変えていかないといけないという意識があります。ただいきなり大きな作品で当事者キャスティングに挑んだとしても、興行的に失敗した際に俳優も作家も次がなくなってしまう。今の日本の状況では残念ながらそれらを懸念して、大きな会社が題材自体から遠のいていることがあると思います。
作家として社会に当たり前にいる人たちを書いていきたい人、書いている人、俳優として組んでみたい人は多くいて、でも、興行的な理由と先ほど仰られた言葉を借りると「リスク」でオフにさせられのはあまり健康的な制作ではないと思います。そしてその結果、当事者が目指せる業界になっておらず、クリエイター側にも当事者がいない状況になっていますよね。だから今は作家側から当事者が参加できる状況をつくってプロデューサーや興行主と組んでいくのが次のステップなんじゃないかと考えています。
若林
なぜトランスジェンダー俳優が活躍できないのかを考えると、まずトランスジェンダーの役がない。じゃあシスジェンダーを演じれば良いと思うかもしれませんが、シスジェンダーを演じるにも身長が足りないとか逆に大きすぎるといった理由から「男性/女性に見えない」といった判断で弾かれてしまう。あとはトランス男性だけで言えば、業界の女性蔑視的な視点から「女性が男性に成り上がってるから面白くない」という考えの人に排除されてしまったり。
藥師
トランスジェンダーはシスジェンダーの役を演じられないというバイアスが浸透していて、オーディションでチャンスが貰えないことが大きな課題ですよね。一方でシスジェンダーがトランスジェンダーの役を演じることは定着していて、近年まで疑問視されていなかった。その突破口となり得るのが当事者キャスティングなので、カミングアウトしている当事者俳優が登用されることには不均衡な構造を変えていく上で意義があります。また、LGBTQ+の俳優を登用する=LGBTQ+のエピソードを入れないといけないと思われているのかもしれませんが、そうではなくLGBTQ+の人が一定いることが”普通”であるということの社会的認知をしてもらいたい。それがまだ追いついてないのかなと。
若林
なぜ当事者が演じた方が良いかの理由のひとつに、見た目の観点もあると思っていて。たとえば過去に関わった作品で、シス男性の俳優がトランス男性を演じたんですが、彼はすごく背が高いんですよね。ただ原作では小さくて小太りという設定だった。一方でお相手となるシスジェンダー女性の俳優は背が低いので、”世間が求める恋愛もの”として成立していたんです。僕みたいに身長が低い人も多いから、そこで葛藤することも結構あるんです。そういう気にする人が多い観点を、表現できず取りこぼしてしまうことがある。そういった部分は当事者だからこそ表現できるものがあると思っていて、大事だと思っています。
藥師
シスジェンダー男性でも背が低い人はいますが、その人たちはシスジェンダーの役ができる。でもなぜ背の低いトランスジェンダー男性はシスジェンダー男性の役ができないのか。そこにはやはり機会の不均衡がありますよね。
加藤
本質的には演じられるのに、「大衆はこういう恋愛映画を求めている」という思い込みが土台となった構造上で機会が奪われているのだと思います。
昨年公開されたパキスタンの映画『ジョイランド』では、同国の長編映画としては初めてトランスジェンダー女性役を当事者が演じていたんです。その当事者キャスティングの重要性について監督にインタビューで質問すると、「それも大事だけど、一番の理由は作品を良くしたいから。当事者が演じることでその人物像がより繊細で信憑性のあるものになる」と答えてすごく納得したんですよね。若林さんのお話を聞いてそのことを思い出しました。
藥師
確かに、当事者キャスティングの大きな意義の一つが「作品がよくなること」である、という視点はとても重要だと思います。また大前提として、シスジェンダーの俳優がトランスジェンダーの役を演じることは可能だと考えていますし、同様に、トランスジェンダーの俳優がシスジェンダーの役を演じることもできると思っています。一方で、俳優に与えられる機会が均衡ではなく、さらに制作現場に専門性をもった監修が十分に入っていないことで、結果としてステレオタイプが再生産され続けている現状を、とても残念に感じています。だからこそ、当事者をキャスティングすることは、作品の質を高めるためにも、業界の構造そのものを変えていくためにも、大きな意義があると考えています。
加藤
俳優ともその話をすることがあるんですが、俳優からしたらやっぱり「色んな役を演じても良い」という気持ちがあるんですよね。僕も原則は何を演じてもいいと思います。が、議論されていることについては、不均衡の状況や表現で誤解をどう招くかといった、演技の話とはまた別の話であることから理解してもらわなければいけません。
若林
ただ様々な俳優の方と話していると、自分にも性のあり方に揺らぎがあることを話してくれる人も中にはいて。「以前は性別に対する葛藤があって、今はそれを受け入れて生きている」というように。それを考えると当事者/非当事者の線引きって完全ではないなって以前から思っているんですよね。だから監修をする際にはいつも「この人にも当事者性があるかもしれない」と考えながらやっています。
当事者キャスティングはもちろん大事なことですが、それはカミングアウトが前提にありますもんね。今の社会状況を鑑みると決して低いハードルではないと個人的にも思います。
若林
そうなんです。だから「これは当事者キャスティングをしていない」という一言では片付けられないこともあると思っていますね。もちろんカミングアウトしている人が演じることは可視化するという意味ですごく重要であるということは大前提にありますが。
「ここが海」のキャスティングについて、俳優である若林さんはどのように考えているのでしょうか?
若林
まず僕個人としては、演じるのが誰であれトランスジェンダーが描かれる作品が増えているのは嬉しいこと。僕の作家仲間も「この時代に扱うには難しい」と考えて、そこをオフにすることがあるんですよ。実際に上演して、炎上や厳しい指摘を受ける可能性もある。その中で加藤さんは可能な限り誠実に向き合ってやってくださったと感じていて、その時点ですごく感謝をしています。加藤さんが仰る通り、いきなり100点のものをつくるのはどうしても難しいですが、今後100点を目指すための土台として今できることがある。今回それを皆で考えながらつくれたのはとても良かったですし、だからこそ鼎談という形で皆の想いをセットで届けることがとても大事だと考えています。
加えて本来であれば何年もかけて変わっていく性別移行の過程を100分で表現するには相当な技量が必要で、その点において黒木さんは素晴らしかった。そこは絶対に言っておきたい。ただ表象という意味で、トランス男性には特有の雰囲気や仕草、喋り方がある。黒木さんはそこに寄せていくことから始めましたが、それを本来持つ当事者の方が演じるのも見てみたかったという思いもあります。
加藤
演劇ですから、また我々以外で上演される可能性もあると思います。キャスティングをする上で難しかったのは、友理は女性として周囲から認識されやすい身体的特徴を持つ人物であること。映画であればスクリーンを一枚隔てているということで観客とレイヤーが違うことと、特殊メイク効果などで監督が見せたい表現ができることもあると思うんですが、観客の目の前で同じ時間を過ごす演劇となると映画と同じ方法では難しいことがあります。作品の性質にも依存する。その場合にどうすればよかったのかは今でも悩んでいます。
若林
特殊メイクを使えば、トランス当事者の俳優が当初の友理を演じるという選択肢もあったと思います。それが加藤さんの作風に合っているかは分かりませんし、トランス男性だけど女性として観客から見られることを苦痛と感じる人もいる。ただもちろんそう感じない人もいますよね。そこはオーディションなどで検討したうえで黒木さんに委ねたんですか?
加藤
そこのオーディションはできていないのが正直なところです。
藥師
友理のようにホルモン投与をしていないトランスジェンダー男性の俳優もいる中で、オーディションをしなかったということは確かに議論すべきポイントです。トランスジェンダーの役を演じるにあたっては、オーディションを行い、トランスジェンダーの俳優を登用するケースは国内外でも少なくありませんし、その意義はとても大きいものです。ただ日本の現状のエンタメ産業で3人芝居をすると考えたときに、知名度や集客性というものはどうしても切り離すことはできないのではないか。その前提がある中でオープンコールのオーディションを開催しても、果たして機会の不均衡は埋められるのか。そういうことも議論した上で、オーディションを実施しなかったと思うんです。もちろん今回のやり方は100点ではないし、足りていなかったこともある。だけど重要なのはこの鼎談などを通じて、これからみんなでどうしていくかという議論をすること。
今後演劇や映画でLGBTQ+の俳優が活躍できる場は増えるために、今回のように協力し合うことで一緒に業界を変えていくことができればと願っています。現状、ジェンダーやセクシュアリティに関する監修が入る作品はまだ多くありません。そのなかで「ここが海」では、研修や脚本制作・広報を担う専門家と、現場で演技を見ながら関わる専門家がセットで作品づくりに参加し、専門性を踏まえた監修体制を導入していただけたことは、大きな一歩だったと感じていますし、なにより制作チームの対話を重ねようとする姿勢は本当にありがたかった。だから良かったところはきちんと認識した上で、足りなかったところを今後皆で変えていくというスタンスで向き合っていきたいなと考えています。
加藤
次のフェーズに進んでいくことを考えたときに、候補者を増やしていくことがすごく大事だと思います。興行主や監督、演出家の立場からしても選択肢は絶対に欲しいはずだし、その候補者を増やすために、ワークショップなどいろんな方法で俳優を発掘できる機会を増やしていけたら良いなと思います。
藥師
ワークショップはぜひお願いしたいです。また現場での演技指導や監修という立場で、当事者の俳優が起用される機会を広げていくことも大切だと思います。
若林
演技レッスンと現場での演技は全く違うんですよ。緊張感も違うし、レッスンで出来たことが出来ないということも往々にしてある。だから如何にして現場で経験を積むかというのはすごく大切です。いきなり主演は難しくとも、例えば学園もので主人公のクラスメイトに起用してもらうなどで現場の経験を積んでいけると良いですよね。クラスに1、2人LGBTQ+がいるのも当たり前ですし、これまで業界であえて省かれていたものがきちんと描かれるようになって欲しいと思います。
キャスティングについては議論の余地は当然あると思う一方、これまで悲劇のフォーマットに落とし込まれてきたトランスジェンダーの物語が、未来に向かっていくものとして描かれてきたのはとても素晴らしいですよね。
加藤
初稿の段階から僕は悲劇としては書いてなかったんですが、「少し悲劇的に捉えられる側面がある」と藥師さんから指摘を受けたことがあったんですよね。その見え方に関してはこちらで100%コントロールした方が良いと思って、悲劇に見えないように少しずつ変更していきました。
藥師
もちろんトランスジェンダー=悲劇というフォーマットにしようという意図はないということは分かっていたんですが、見方によっては「友理がカミングアウトしたことで家族に不幸が生まれた」というように捉えられる描写があったので、その点は対話をしました。でもその結果もあり、最終的なラストは私自身すごく好きなものになりました。台本で「愛の空気が続く」とト書きされていた通り、家族の愛が続いていくような終わり方で。
若林
作られたラストシーンというより、本当にただ日常が続いていくという感じですもんね。センセーショナルにしようとしていなくてすごく素敵でした。
物語の捉えられ方に関連して伺いたいのですが、加藤さんは作り手として「どこまで観客に解釈を委ねるか」についてはどのように考えているんですか?
加藤
全員がそうとは言いませんが、意図をすべて喋りたい人っていないと思うんです。そこは観客に委ねたいし「なんでそこまで喋らなきゃいけないんだろう」とも思う。でも今回の企画のフローに関しては、取り組み部分をもっとちゃんと喋った方が良かったなというのは反省点としてあります。
演劇界、映画界それぞれでいろんな議論があると思うんですが、今回のような取り組みや、それぞれの作り手ができることは取り組めばいいし、相談できる人を増やしていくべきじゃないでしょうか。たとえば今、ジェンダーセクシュアリティを題材とした作品を作ろうとしたとき、誰を信頼して、どうやって頼ればいいのかわからない人って結構いるんじゃないかと思います。でもこの鼎談のような場所で発信していけば次に繋がるかもしれない。僕みたいに自分の中だけで考える人も大勢いると思いますし。
特に「ここが海」はチーム体制で全体を監修したという点で、現段階でのモデルケースの一つとして知ってもらえると良いですよね。
藥師
今回監修に予算を充てることや、サイトや記事を丁寧に作ることを決めたのはアミューズさんなんです。担当の方々もとってもアライで、チームとして、そしてカンパニーとしてメッセージをちゃんと届けたいという意識がすごくあった。まだまだLGBTQ+が表層的に描かれることが多い中で、いろんなところに掛け合って、丁寧に積み上げてくれた姿勢が本当にありがたかったし、それはぜひ知ってもらいたいです。もちろんアミューズさんを含め業界的な課題はあるので、、今後は当事者俳優や制作者を育成・応援する仕組みや、監修者のネットワークをエンタメ業界全体で一緒に作っていくような大きな流れが日本でもできたら良いなと思っています。
加藤
演劇をやっている資本の大きな会社は限られていますが、やはりリスクを恐れて題材を選んでしまうところがある。その中で一歩踏み出してくれたのは良いことだと思います。
若林
これが業界のスタンダードになっていってくれると嬉しいですよね。
加藤
皆経済力もやりたいことも違うので、「一気にこうしよう」とできるものではないんですが、少しずつフェーズが変わっていく中で、それぞれが現在地を確認しながら自分なりに取り組んでいけたら良いなと思います。一つの作品で何かが大きく変わることはないですが、いろんな意志と作品が集まれば進めていけるものなので。「ここが海」がその一つになれたのであれば良いなと思っています。
取材・テキスト:ISO
撮影:山岸和人